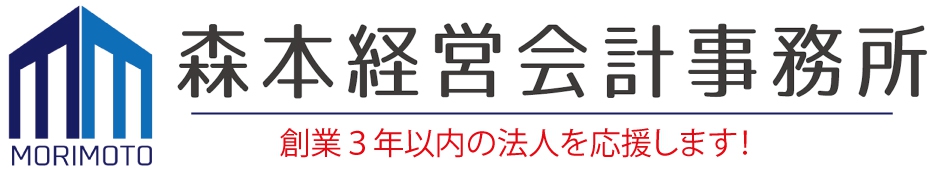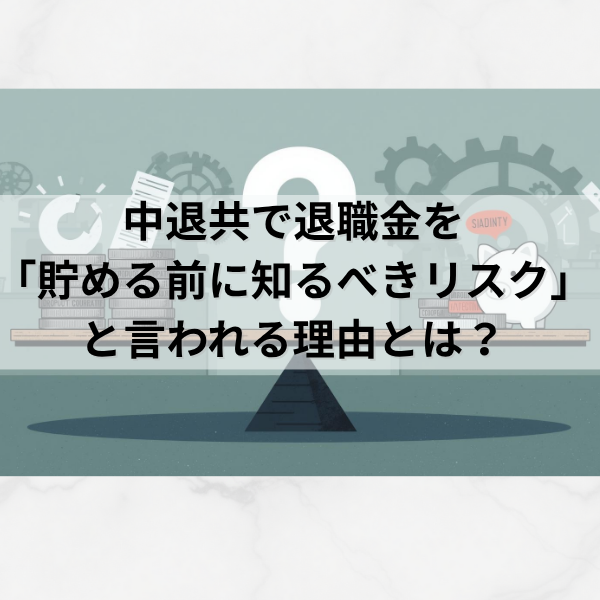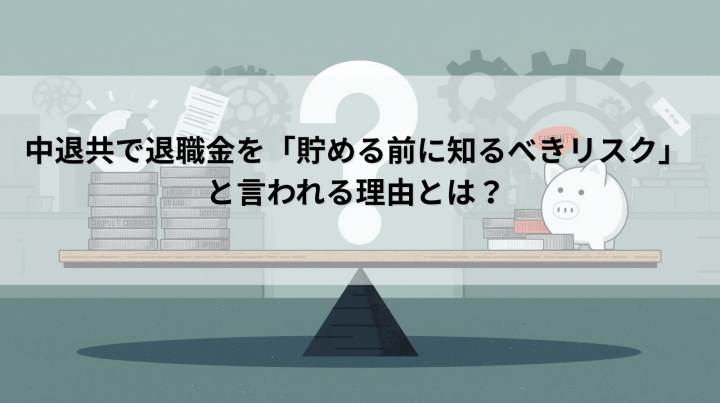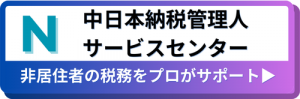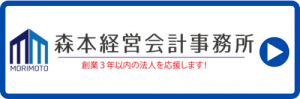💰 中退共で退職金を「貯める前に知るべきリスク」と言われる理由とは?特退共との違いを税理士が解説
中小企業の経営者から「退職金は中退共で積み立てるのが一番い
・・・(続きはこちら)
💰 中退共で退職金を「貯める前に知るべきリスク」と言われる理由とは?特退共との違いを税理士が解説
中小企業の経営者から「退職金は中退共で積み立てるのが一番いいのでは?」という相談をよく受けます。
確かに、中退共(中小企業退職金共済制度)は国が運営する安心な制度で、掛け金は全額損金にでき、助成金も受けられるなどメリットが多い制度です。
しかし、実務の現場では「中退共で退職金を貯めてはいけない」と言われることもあります。今回はその理由と、もう一つの選択肢である「特退共(特定退職金共済)」との違いを税理士の立場から解説します。
1. 中退共とは?【制度の基本】
中退共は、事業主が毎月掛け金を支払い、従業員が退職した際に中退共機構から直接退職金が支払われる仕組みです。
- 掛け金は月5,000円から3万円まで選択可能
- 掛け金はすべて経費(損金)として処理できる
- 加入時に助成金が出る場合がある
導入のハードルは低く感じられますが、実務上の制約もあります。
2. 「貯めてはいけない」と言われる3つの理由
理由① 短期間の退職で元本割れのリスクがある
まず大きな理由が、短期間で退職すると元本割れになる点です。加入1年未満では退職金が支給されず、2年程度でも掛け金総額を下回ることが多いのです。
従業員の入れ替わりが多い企業では、積み立てた資金が実質的にムダになる可能性があります。
理由② 掛け金の減額や脱退が難しい
次に、掛け金の減額や脱退が難しい点も問題です。経営が厳しくなっても、掛け金を下げるには従業員の同意と手続きが必要で、実際には簡単に変更できません。
さらに、制度を途中でやめることも難しく、「最初の補助金につられて始めたけど後悔した」という声も少なくありません。
理由③ 会社の運転資金には一切充てられない
加えて、積み立てたお金を会社で使うことができないという制約もあります。中退共の掛け金はあくまで従業員の退職金であり、資金繰りが厳しくても会社の運転資金には充てられません。
キャッシュフローが不安定な企業には負担が重くなるケースもあります。
3. 特退共(特定退職金共済)という選択肢
そこで検討されるのが「特退共(特定退職金共済)」です。商工会議所や団体が運営しており、中退共よりも柔軟な運用が可能です。
特退共の主な特徴
- 掛け金が1口1,000円単位など柔軟に設定できる。
- より小規模・地域密着型の事業者には使いやすい。
- 中退共と併用できる場合もある。
ただし、特退共も万能ではありません。掛け金の減額や脱退には従業員の同意が必要な場合もあり、転職先で通算できない制度もあります。
4. まとめ:退職金制度は「経営判断」が重要
中退共は制度としての信頼性が高く、従業員が長く勤める企業には適しています。一方で、勤続年数が短い業種や資金繰りに波がある会社では、掛け金の固定化がリスクとなることもあります。
特退共は掛け金の柔軟性が高く、少人数の企業や業績変動がある会社に向いています。
⚠️ 要点
助成金につられて安易に中退共に加入すると、後で身動きが取れなくなることもあります。退職金制度は「節税」ではなく「経営判断」です。
自社の資金繰り、社員の定着状況、将来の経営計画を踏まえて選ぶことが大切です。
■ 当事務所から
退職金制度は一度始めると簡単にやめられません。中退共・特退共のどちらが自社に合うか、数字をもとに冷静に検討することをおすすめします。